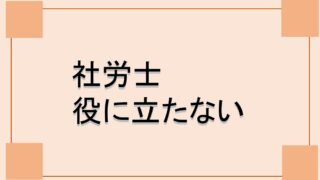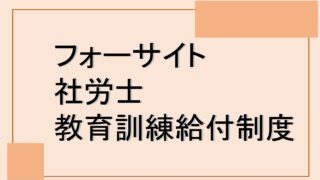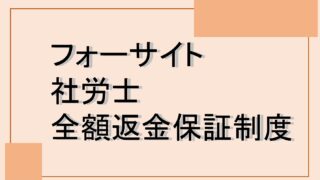<人気講座ランキング(上位3社)>
第1位 スタディング![]() :高品質なのに業界最安価格:46,800円~
:高品質なのに業界最安価格:46,800円~
第2位 フォーサイト![]() :全国平均の3.72倍!、業界最高の合格率
:全国平均の3.72倍!、業界最高の合格率
第3位 アガルート![]() :全国平均の3.16倍、高い合格率と全額返金サービス
:全国平均の3.16倍、高い合格率と全額返金サービス
=>社労士の通信講座おすすめ18社の比較・ランキングの記事はこちら
社会保険労務士(社労士)は、毎年4万人前後の方が受験する人気の資格です。
そのため、社労士資格に興味を持っている方も多いことでしょう。
そのような方の多くが「社会保険労務士(社労士)の難易度はどの程度? 他の国家資格と比べるとどうなの?」と疑問を持っていると思います。
そこで、今回の記事では、社労士資格の難易度について多角的に調べた結果について書いていきます。
社労士に興味がある方、ぜひ参考にしてくださいね。
なお、社労士試験の「最速合格勉強法」について、クレアールが、受験ノウハウの詰まった市販の書籍を、今だけ【0円】無料でプレゼント中です。
【0円】無料なので、ぜひ入手して読んでみてください。
<クレアールに応募すると、社労士受験生向けの市販の書籍「非常識合格法」がもらえる【0円】無料>
クレアールの社会保険労務士(社労士)講座に資料請求を行うと、全国の書店で販売中の社労士受験ノウハウ書籍が【0円】無料でもらえます。
試験に関する最新情報や、難関資格に「最速合格」するためのノウハウを凝縮。
社労士受験ノウハウ満載の市販の書籍が【0円】無料で進呈されるので、ぜひ入手してください。
試験の合格率からみた、社労士の難易度
社労士試験の受験者数・合格者数・合格率の推移
社会保険労務士(社労士)とは、労働法や社会保険に関する正しい知識を持つプロフェッショナルです。
就業規則や社会保険の手続きに関する書類を作成したり人事コンサルタントをしたりと、社会保険労務士(社労士)の業務内容はたくさんあります。
毎年4万人前後の方が受験する人気の資格ですので、社労士の難易度が気になっている方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、社会保険労務士(社労士)は難易度の高い資格です。
社会保険労務士(社労士)の難易度が高い理由を証明するために、ここでは過去15年間で社労士の合格率がどう推移しているのかまとめてみました。
<実施年度 受験申込者数 受験者数 合格者数 合格率>
平成16年 65,215人 51,493人 4,850人 9.4%
平成17年 61,251人 48,120人 4,286人 8.9%
平成18年 59,839人 46,016人 3,925人 8.5%
平成19年 58,542人 45,221人 4,801人 10.6%
平成20年 61,910人 47,568人 3,574人 7.5%
平成21年 67,745人 52,983人 4,019人 7.6%
平成22年 70,648人 55,445人 4,790人 8.6%
平成23年 67,662人 53,392人 3,855人 7.2%
平成24年 66,782人 51,960人 3,650人 7.0%
平成25年 63,640人 49,292人 2,666人 5.4%
平成26年 57,199人 44,546人 4,156人 9.3%
平成27年 52,612人 40,712人 1,051人 2.6%
平成28年 51,953人 39,972人 1,770人 4.4%
平成29年 49,902人 38,685人 2,613人 6.8%
平成30年 49,582人 38,427人 2,413人 6.3%
令和元年 49,570人 38,428人 2,525人 6.6%
令和2年 49,250人 34,845人 2,237人 6.4%
社会保険労務士(社労士)の合格率のデータを見てみると、かなりの難易度が高い資格だとわかります。
社労士の合格者数や合格率は年ごとに増減する傾向があり、合格率の平均は毎年6%前後ですが、平成27年度の試験では2.6%でした。
「15名が受験して1名が合格できるか」という試験ですので、社会保険労務士(社労士)の資格の難易度が非常に高いことがわかりますね。
社労士試験の合格率が低い理由とは?
なぜ社労士試験の合格率は低いのでしょうか?
まず、受験科目数の多いことが挙げられます。詳しくは後述しますが、全部で10科目あり、しかも科目合格制度はありません。つまり、すべてを1度に受験しないといけないのです。
さらに、10科目全体でトータルの基準点をクリアするだけでは駄目で、試験科目ごとに細かく設定された合格基準点(ボーダーライン、いわゆる足切り)をクリアする必要があります。
社労士試験には、科目ごとに選択式(5点満点)と択一式(10点満点)があります。それぞれの科目の合格基準点は、選択式の場合は2~3点、択一式は4点となっています。
このうち、合格基準点に満たないものが1科目でもあれば、不合格になります。決して苦手科目を作ってはならない、ということがおわかりでしょう。
※科目ごとの合格基準点(足切り)は、特に選択式試験において対応が難しいと言われますが、この点についても後述します。
以上のような厳しい試験制度が、社労士の合格率を低くしている理由です。
合格率から見た難易度ランキング~他の試験との比較
続いて、主要な他の国家資格と合格率をランキングにしてみました。
| 資格名 | 合格率 |
| 司法書士 | 約3~4% |
| 社労士(社会保険労務士) | 約6% |
| 中小企業診断士 | 約4~8%(一次・二次ストレート) |
| 行政書士 | 約10~13% |
| 宅建(宅建士) | 約15% |
上記では、いずれも難関とされる国家資格と比較しましたが、そのなかでも社労士の合格率は低い方であることが分かります。
著名な資格である「行政書士」「宅建」の合格率は10~15%であり、社労士の合格率はそれらの約半分ですから、いかに難易度が高いか、というのが実感できると思います(あくまで、合格率から見た難易度です)。
※社労士の合格率については、下記の記事も参考にしてみてください。

平均受験回数から見た、社労士の難易度
社労士の合格率が低い、ということは、社労士の試験では一発合格は難しい、ということです。
実際、社労士を受験した人の平均回数は4回~5回と多くなっています。
「4回~5回」というのは、あくまで平均の回数ですから、実際には合格までもっと多く受験をされる方も少なくありません。
このような受験回数の多さをみても、社労士の難易度の高さが実感できるかと思います。
なお、それでも毎年数多くの方が社会保険労務士(社労士)の試験を受験するのは、人事パーソンとしてのキャリアアップに繋がるからです。それだけの価値がある資格、ということですね。
※社労士試験の平均受験回数については、下記記事も参考にしてください。

勉強時間から見た、社労士の難易度ランキング
資格試験において「合格に必要な勉強時間」は、その資格の難易度と大きく関係します。
まずは社労士の合格までの勉強時間について、大まかな目安を見ていきましょう。
- 独学での勉強時間は1,000時間程度
どれだけ短くても、800時間以上の勉強は必要です。
つづいて、他の国家資格の勉強時間は以下のとおりです。
- 弁護士(司法試験予備試験):約6,000時間
- 司法書士:約3,000時間
- 不動産鑑定士:約2,000時間
- 中小企業診断士:約1,000~1,200時間
- 社会保険労務士(社労士):約1,000時間
- 行政書士:約500~800時間
- 宅地建物取引士:約300時間
- 日商簿記2級:約250時間
一般的に「難関」とイメージされる資格試験ほど、勉強時間が多くなっています。
法律系の資格試験の頂点である司法試験は6,000時間。仕事をせずに専業で受験勉強に集中しても5年以上かかることもある、超難関資格ですね。
司法書士は、必要な勉強時間は3,000時間程度であり、合格でに3~4年以上かかることが一般的です。
1,000時間程度必要な中小企業診断士や社労士試験は、「仕事をしつつ勉強して合格できる試験としては最も難易度が高い」と言われます。
1日3時間の勉強を1年続け、ようやく1,000時間を超えますから、確かに仕事と勉強を両立できる上限かも知れませんね。
※社労士の勉強時間については、下記の記事も参考にしてみてください。

偏差値のランキングから見た、社労士の難易度
ここでは、某掲示板サイトや口コミサイト等から引用した「資格難易度・偏差値ランキング」から社労士の偏差値について考えてみます。※現実には国家資格には偏差値は存在しません。あくまで目安となります。
社労士の偏差値は60、中程度の難易度?
上記のランキングの中では、社労士・中小企業診断士・行政書士などが偏差値60~59で並んでいました。
これらの資格は「働きながら合格できるレベルでは最難関」と言われることがありますが、上記の表を見てみると、社労士等の難易度は、難関国家資格(士業)の中では、標準的といった位置づけではないでしょうか。
社労士の難易度と大学の難易度を比較
社労士の資格偏差値は60ですが、偏差値60の大学というと、どのような大学・学部になるのでしょうか。東進ハイスクールの大学入試偏差値ランキングから、偏差値60の大学(学部)をご紹介します(一部の国公立大学文系学部を抜粋)。
- 和歌山大学(教育)
- 富山大学(人文)
- 岡山大学(教育)
- 新潟大学(法)
など
社労士の難易度 ~他の資格との個別比較
ここでは、社労士試験と他の国家試験等について個別に難易度を比較してみましょう。
社労士の難易度 宅建との比較
宅建(宅建士)は不動産取引のエキスパートを育成する国家資格です。
宅建の合格率は約15%であり、また合格に必要な勉強時間は300時間程度と言われています。
合格率・勉強時間から、宅建より社労士のほうが難易度が高いことが分かります。
※社労士と宅建士の難易度の比較について詳しくは、下記の記事もチェックしてみてください。

社労士の難易度 司法書士との比較
司法書士は、商業登記・不動産登記を主業務とする専門家の資格です。
社労士試験以上に試験科目が多く、司法試験に近い難易度があります。
司法書士試験の合格率は3%、また合格に必要な勉強時間は3,000間程度と、いずれも社労士試験を圧倒しています。
つまり、司法書士試験の難易度は社労士試験とは比べものにならないぐらい高いと言えるでしょう。
社労士の難易度 行政書士との比較
行政書士は、行政事務と書類作成の専門家です。
行政書士試験の合格に必要な勉強時間は500~800時間、合格率は10~15%であり、いずれも社労士試験を下回ります。
難易度を比較すると、行政書士試験の方が難易度はやや低いといえるでしょう。
※社労士と行政書士の難易度の比較について詳しくは、下記の記事もチェックしてみてください。

社労士の難易度 税理士との比較
税理士はクライアントの依頼に応じて、税務書類の作成や税務申告の代行を行う、税理士は税金に関する専門家です。
税理士試験は、11科目中5科目に合格すれば資格を取れます。ただし、税務の専門家だけあって、理論と数的処理の難解な問題が多く、それぞれの科目の難易度は非常に高いです。
一方で、科目ごとの受験が認められているのは税理士試験の大きな特徴です。そのため「1年につき1科目、5年で合格をめざす」というように、働きながら受験する方は長期間かけて取り組むケースがほとんどです。
勉強時間の合計が2,500時間かかるなど、社労士より難易度の高い試験であることは間違いありません。
※社労士と税理士の難易度の比較について詳しくは、下記記事もチェックしてみてください。

社労士の難易度 弁護士との比較
ご存じのとおり、文科系国家資格の頂点ともいえるのが弁護士。
当然ながら、社労士と比べても格段に難易度が高い資格です。
弁護士になるためには、まず予備試験に合格するか法科大学院を修了することが必要。その次に司法試験を受験します。トータルで6,000時間以上の勉強が求められます。
ただ、一度弁護士登録すれば、社労士・弁理士・税理士・行政書士などの登録も出来ちゃいます。「弁護士登録すれば・・・」という点がハードルが高い訳ですが、そこさえ乗り越えれば社労士+弁護士という兼業も可能な訳です。
少し話が脱線しましたが、それだけ弁護士の難易度が高いということでしょう。
※弁護士と社労士のダブルライセンス等については、下記記事も参考にしてみてください。

社労士の難易度 弁理士との比較
弁理士は知的財産に関する専門家で、以下のような業務を行います。
- 「特許出願におけるサポート」
- 「実用新案登録出願の必要書類の作成」
- 「意匠出願や商標出願の書類の作成」
- 「知的財産権に関する相談」
合格率こそ6~8%と社労士と同等ですが、3,000時間程度の学習が必要なため、社労士よりは難易度が高いといえるでしょう。
社労士の難易度 土地家屋調査士との比較
土地家屋調査士とは、不動産の表示に関する登記の申請手続などを行う専門資格のことです。
必要な勉強時間は1,000~1,200時間程度、また合格率は6%~7%と低くなっており、社労士と比較すると同等程度の難易度になります。
社労士の難易度 不動産鑑定士との比較
不動産鑑定士は土地の公示価格を決めることが主な業務であり、最終合格率は2%~3%と宅建よりも遥かに難易度が高くなっています。
また資格取得のためには、試験合格後に1~2年の実務修習を受ける必要があり、社労士試験と比べてもかなりハードルの高い資格といえるでしょう。
社労士の難易度 簿記2級との比較との比較
簿記2級は一般企業の経理のレベルを想定した試験です。
合格率や勉強時間で比較してみると、社労士に比べ簿記2級はかなり難易度が低いと考えられます。
社労士の難易度 中小企業診断士との比較との比較
中小企業診断士は経営コンサルタントの国家資格であり、その試験範囲は広範なものとなっています。
経営戦略・マーケティングから財務・会計、ITや法務などについても出題され、必要な勉強時間は1,000~1,200時間となります。
また、1次試験と2次試験に分かれており、これらをストレートで突破する合格率はわずか4%しかありません。
社労士と同等または多少難易度の高い試験といえるでしょう。
※社労士と中小企業診断士の難易度の比較について詳しくは、下記記事もチェックしてみてください。

社労士の難易度 気象予報士との比較
気象予報士とは、気象庁から提供された情報を分析して天気の予測業務を行う、気象予報のスペシャリストです。
気象予報士になるには、気象庁から提供される気象データを理解し、応用する能力が必要です。
学科試験と実技試験の両方の受験が必要で、予報業務に関する一般知識・専門知識が出題されます。
社労士とは学習内容こそ異なるものの、勉強時間は1000時間以上・合格率は4~5%程度であり、難易度は似ていると言えるでしょう。
社労士の難易度 メンタルヘルスマネジメント検定(Ⅰ種)との比較
メンタルヘルスマネジメント検定(Ⅰ種)は、企業内でメンタルヘルス対策を啓蒙・推進する立場(管理職・人事部等)の方に向けた検定資格です。
メンタルヘルスマネジメント検定は、人事系資格ランキングの中で人気は高いですが、合格までの勉強時間は約120時間・合格率は約10%と、どちらの観点からも社労士の方が大幅に難易度が高いことが分かります。
社労士の難易度 キャリア・コンサルタントとの比較
キャリアコンサルタントは、平成28年4月より国家資格なったばかりの比較的新しい資格です。
キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルティングを実施するプロフェッショナルであり、厚生労働省の定義によると、キャリアコンサルティングとは「労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うこと」とされています。
こちらも社労士と同じ人事系資格ですが、キャリアコンサルタントの勉強時間は約100時間・合格率は約40%と、社労士に比べ難易度はかなり低くなっています。
社労士の難易度 FP1級との比較
FP(ファイナンシャルプランナー)は個人や家庭のお金に関する深い知識を持ち、顧客をサポートする専門家です。
そのなかでもFP1級は最上位の資格であり、500~600時間の勉強時間・平均合格率10%程度となっています。社労士の難易度よりは低い資格といえるでしょう。
※社労士とFPの難易度の比較について詳しくは、下記記事もチェックしてみてください。

社労士の試験内容からみた難易度
ここまで見て、社労士試験は合格率が低く、多大な勉強時間が必要な難易度の高い試験であることが分かったと思います。
ここからは、社労士試験の内容から難易度の高さを考察していきましょう。
社労士の難易度が高い理由 ~受験資格が定められている
国家資格の中には、年齢や学歴に関わらず誰でも受験できる試験があります。
社会保険労務士(社労士)の試験の場合は、次の3つのいずれかの受験資格を証明しないといけません。
- 学歴(大学や短期大学、専門職大学を卒業している)
- 実務経験(実施事務に従事した期間が通算して3年以上など)
- 厚生労働大臣が認めた国家試験合格(社会保険労務士試験以外の国家試験のうち厚生労働大臣が認めた国家試験に合格したなど)
誰でも自由に受けられる試験ではないことは、社会保険労務士(社労士)の資格取得のハードルを高くする要因の一つと言えるでしょう。
※社労士試験の受験資格について詳しくは、下記の記事を参考にしてください。

社労士の難易度が高い理由 ~試験範囲が広くて知識の整理が難しい
試験範囲の広さも、社会保険労務士(社労士)の難易度が低い理由の一つです。
社会保険労務士(社労士)の試験は、次の科目について行われます(以下は択一式の場合)。
- 労働基準法及び労働安全衛生法(10問10点)
- 労働者災害補償保険法(10問10点、徴収法3点分を含む)
- 雇用保険法(10問10点、徴収法3点分を含む)
- 労務管理その他の労働に関する一般常識・社会保険に関する一般常識(10問10点)
- 健康保険法(10問10点)
- 厚生年金保険法(10問10点)
- 国民年金法(10問10点)
科目ごとの広範な知識をバランス良く習得して、高いレベルを維持したまま試験の合格点に達するのは並大抵のことではありません。
多くの社会保険労務士(社労士)の受験生は試験までに十分な対策を立てられないため、「何度受けても試験に合格できない…」と悩む方が多くいるのです。
社労士の難易度が高い理由 ~長丁場の試験時間に堪えないといけない
社会保険労務士(社労士)の試験は、次のスケジュールで行われます。
- 午前中は選択式試験で10時30分~11時50分までの80分間
- 午後は択一式試験で13時20分~16時50分までの210分間
途中に1時間のお昼休みがありますが、トータルで290分間もの試験を受けないといけません。
午前中の社会保険労務士(社労士)の試験だけで力を使い果たして、午後の試験には集中力が切れてしまう受験生も少なくありません。
他の資格試験と比べて試験時間が長丁場なのは、社会保険労務士(社労士)のハードルの高さの1つです。
社労士の難易度が高い理由 ~法改正による最新の情報に対応できない
社会保険労務士(社労士)の試験は、ほとんどが法令科目です。
日本で定められている法律には法改正があり、毎年のように変わっているケースも少なくありません。
つまり、社会保険労務士(社労士)の受験生は、法改正で一度覚えた制度や条文をリセットして試験勉強に取り組む必要があります。
最新の情報に対応できていないと、社会保険労務士(社労士)の試験で不合格になりやすいわけです。
難易度の高い社会保険労務士(社労士)に合格するには、最新の法改正情報を正確に把握して本試験で正解を導き出すことが求められています。
社労士の資格とは? 業務内容の紹介
ここまで、様々な角度から社労士試験の難易度を説明してきました。
ここでは、社労士資格に興味を持ち始めたばかりの方に向けて、
- 社労士とはどんな資格なのか?
- 具体的な仕事(業務)の内容は?
などの疑問に対し、分かりやすく説明していきましょう。
社労士資格の概要
社会保険労務士(社労士)は簡単に説明すると、労働法や社会保険に精通しているプロフェッショナルです。
企業における労働や社会保険に関する諸問題を解決したり、個人の年金の相談に応じたりと幅広い業務内容をこなします。
企業が成長するに当たり、「お金」「モノ」「人材」の3つが欠かせません。
その中でも、社会保険労務士(社労士)は人材に関する専門家と考えるとわかりやすいですね。
労働法や社会保険に関する書類の作成や提出は独占業務に分類されますので、社会保険労務士(社労士)の資格を持つ者にしか許されていません。
企業で勤務すれば安定した収入を見込めますし、将来的に独立開業して働く選択肢もありますので、社会保険労務士(社労士)は30代~40代を中心にビジネスマンから人気の資格です。
【注意!】実務経験が豊富な人は落ちてしまうことも
ここまで社労士の業務内容を説明して来ました。
ただ、これから社労士試験を受験するなら、豊富な実務経験が足かせになってしまうケースもあるので注意してください。
というのも、「実務で使うノウハウ」と「試験で問われる知識」は違うからです。
実務に役立つ知識よりも、テキストに記載されている各科目の法律知識の方がはるかに重要です(試験対策としては)。
なまじ実務を知っていると、「机上の智識は使えない」「その知識は実務では使えない」など、斜に構えたような態度を取る方がいらっしゃいますが、
そのような態度では合格はおぼつかないことを肝に銘じておくべきです。
社労士が人気の理由
難易度が高いにも関わらず人気の社労士資格。
ここでは、その理由をまとめてみました。
会社の仕組みを学ぶことができる
社会保険労務士(社労士)の資格を取得する勉強をすると、下記のように会社の仕組みについての理解を深められます。
- 企業で従業員が働く上で必要な就業規則
- 社会保障分野の一つの社会保険
- 会社を退職した後の年金問題
これらは全て従業員が会社で健全に働くために欠かせません。
社会保険労務士(社労士)になると自然と企業に関わる決まり事や従業員の権利を学べますので、「知識がある」⇒「自分の身を守れる」と繋がります。
社会人として働いていくに当たり、会社がどう成り立っているのか知るのは意外と重要です。
資格取得の知識を仕事に活かせる(収入アップや昇進などに繋がる)
資格取得の知識を普段の仕事に活かせるのは、社会保険労務士(社労士)の大きなメリットです。
現に社会保険労務士(社労士)の合格者の6割以上は、既に社会人として働いています。
社会保険労務士(社労士)の資格を取得することで、具体的にどう仕事に活かせるのか見ていきましょう。
- 管理職や人事の方は労働を学ぶことにより、コンプライアンスに即した働く人に優しい労務管理ができる
- 総務や経理の方は、労働保険や社会保険の給与計算で法律に基づく正確な処理ができる
- 人事部門でも労務部門でも替えの利かない存在として社内でポジションを獲得できる
自社に社会保険労務士(社労士)がいると、「経営上の課題を解決してくれる」「労働環境整備のコスト削減に繋がる」「助成金を獲得できる」といった企業側のメリットがあります。
つまり、社会保険労務士(社労士)を持つあなたは社内でも特別な存在になりますので、昇給や昇進のチャンスが舞い込んでくるのは間違いありません。
社会保険労務士(社労士)の試験は難易度の高い国家資格ですので、スキルアップやステップアップに役立ちますよ。
就職や転職で大きな武器になる
業種や職種で変わりますが、社会保険労務士(社労士)の資格は就職や転職で大きな武器になります。
下記に該当する企業や会社は、社会保険労務士(社労士)の有資格者を急募で探しているケースが多いのです。
- 事業の拡大に伴って人事や労務関連の社内整備が必要になった
- 会社の新規立ち上げで労働保険や社会保険に精通する人材が必要になった
一般企業の人事課や経理課だけではなく、社会保険労務士法人や個人事務所も決して例外ではありません。
就職や転職で応募できる求人の選択肢の幅が広がるのは、社会保険労務士(社労士)の資格を取得するメリットの一つです。
※社会保険労務士(社労士)の資格が就職や転職で役立つ理由については、こちらのページでも解説しています。

将来的に独立開業の道が開ける
サラリーマンとして企業勤めしている方は、「独立なんてあり得ない」と考えるかもしれません。
しかし、社会保険労務士(社労士)の資格を持っていれば、将来的に独立開業の道が開けます。
社会保険労務士(社労士)を取得した後の働き方は、大きくわけると次の3つです。
- 会社の人事や総務で保険関係の手続きや就業規則の作成を行う企業内社会保険労務士
- 各企業の労務管理だけを請け負う社会保険労務士事務所の社員
- 自分で独立開業して事務所を持つ独立社労士
独立開業すると自分で開業して自分の事務所を構える形になりますので、自分が組織のトップに立ちます。
企業内社会保険労務士とは違った苦労や壁がありますが、社会保険労務士(社労士)の資格を活かして独立するのは決して不可能ではありません。
社会保険労務士(社労士)として独立すると、自分自身の裁量で働けたり大幅に年収アップができたりといったメリットがあります。
社会保険労務士(社労士)としての活躍の幅を広げることができますので、将来の選択肢の一つに加えてみてはいかがでしょうか。
社労士の独立・開業については、下記の記事にくわしくまとめてありますので、良かったら参考にしてみてください。

どうしても独学が難しければ、通信講座の利用も検討する
ここまで独学の勉強方法を説明して来ました。
ただ、社労士試験はあまりにも難易度が高いので、独学に限界を感じる方もいるでしょう。
そんな時は通信講座の検討も視野に入れてみてください。通学講座はまだまだ高額ですが、通信講座は価格も手ごろになってきています。
社労士通信講座の種類は多いですが、そんな時は各社の講座の特長を分析したサイト「知識ゼロから社会保険労務士へ」が分かりやすいので参考にしてみてください。
当サイトでも各社通信講座の解説などしていますが、セカンドオピニオンとして複数の情報をチェックするのがおすすめです。
詳細は下記のリンクからご確認ください。
≫参考:知識ゼロから社会保険労務士へ
社会保険労務士(社労士)は大学生にとって難易度が高い?
大学生のうちに将来に向けて、社会保険労務士(社労士)の資格試験の勉強を始める方が多く見られるようになりました。
上記では社会保険労務士(社労士)の受験資格は大学や短期大学卒業と記載しましたが、大学生は例外的に卒業必須単位62単位以上を取得していると試験を受験できます。
つまり、大学の在学中に勉強を積み重ねて社会保険労務士(社労士)に合格するのは決して不可能ではありません。
しかし、社会保険労務士(社労士)は大学生にとって難易度が高過ぎる資格なのではと、疑問に感じている方は多いのではないでしょうか。
社会保険労務士(社労士)は合格率の低い試験ですが、社会人と比較してみると大学生には時間があります。
もちろん、大学でも単位を取得するための勉強や試験対策が必要でも、社会人になって働きながら資格取得の勉強をするよりかは遥かに楽です。
2018年度の社会保険労務士(社労士)合格者の中で学生は僅か0.5%と少ないのですが、それだけ価値のある資格ですので、大学生の方は試験勉強を早めにスタートしてみてはいかがでしょうか。
新卒の大学生に社会保険労務士(社労士)の資格が向いている理由
新卒の大学生には、次の理由で社会保険労務士(社労士)の資格が向いています。
- 難易度の高い社会保険労務士(社労士)の資格を持っているだけでも、他の学生と比べて一歩も二歩もリードしている
- 法人社労士の事務所や法人税理士の事務所、経営コンサルティング会社への就職で役立つ
- 一般企業への就職でも人事部や総務部で重宝される
- 計画的に努力して結果を出す能力やスキルを持っていると採用担当者にアピールできる
就職活動で内定を獲得するためには、採用側の印象に残る学生でないといけません。
社会保険労務士(社労士)の資格を持つ大学生は少ないからこそ、採用担当者の印象に残って内定獲得が有利になるわけですね。
「社会保険労務士(社労士)を持っていても未経験なら意味がないのでは?」と考える大学生は少なくありません。
しかし、就職したことのない大学生に実務経験がないのは当たり前で、企業側はポテンシャルを見込んで採用活動を行います。
通常であれば経験がないと就職が難しい企業や部署でも、社会保険労務士(社労士)の資格を持つ大学生は一目置かれた存在になるでしょう。
ただし、大学生のうちから社会保険労務士(社労士)の試験を受験する場合は、実際の労務関係や社会保険関係の実務を知らない状態です。
学習内容に実感が持てずに挫折する方もいますので、「絶対に合格するぞ!」という熱意やモチベーションが大事だと心得ておいてください。
※大学生が在学中に社労士を取得するメリットやデメリットについては、下記記事で詳しく解説していますので、よろしければこちらもどうぞ。

まとめ
以上のように、社会保険労務士(社労士)の試験の難易度、他の資格との比較や偏差値ランキングについてまとめました。
平均して合格率が6%前後の社会保険労務士(社労士)は、間違いなく難易度の高い資格です。
合格率が低いのは、「受験資格がある」「試験範囲が広い」「選択式試験が難しい」など、試験内容だけ見ても様々な理由がありますね。
しかし、社会保険労務士(社労士)の資格を持っているだけで業務や就職、転職に役立てることができますので、今から試験勉強を始めてみてください。