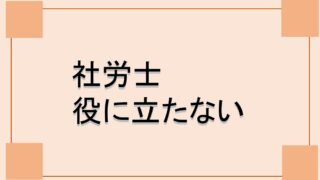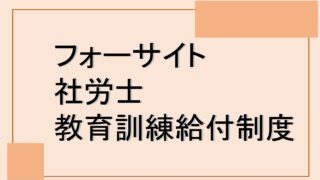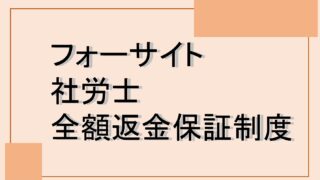「社労士試験は暗記が重要。でも自分は暗記には自信がない。どうしよう?」
などと考えている受験生の方も多いのではないでしょうか?
確かに、社労士試験の出題範囲は非常に膨大です。暗記なくして合格できないことは間違いないでしょう。
とは言え、丸暗記すれば乗り切れる、というものでもありません。
それでは、具体的には、どうすればよいのでしょうか?
この記事では、社労士試験における暗記の適切な方法やポイントの押さえ方について、わかりやすく解説していきます。
ぜひ記事を参考にして頂き、社労士試験の暗記を乗り越えて頂ければと思います。
社労士試験に暗記が有効な理由
社労士試験は選択式と択一式の2種類の形式で問われますが、いずれもマークシートであり、論文や面談などは一切ありません。
そのため、関係法令の条文や解釈等を詳細に理解することよりも、条文上のキーワードや数値などの暗記を優先することのほうが試験攻略には有効、という側面があります。
しかし、何でもかんでも丸暗記すればよい、というものではありません。
以下、社労士試験対策における暗記の適切なポイントについて説明します。
完璧に暗記することを目指さない
社労士試験の暗記において、まず留意することは「完璧を目指さない」ということです。
「どんな問題が出題されても、スラスラ解答したい!」
などと考えている完璧主義者の方は要注意です。
前述のとおり、社労士の出題範囲は膨大なので、「すべてを丸暗記に頼ろう」とすると、時間不足で試験勉強の計画が崩壊してしまう可能性が非常に高くなります。
基本&出題傾向が高い事項に絞って暗記する
そうならないためには、暗記に入るまえに「出題傾向の徹底分析」が重要となります。
社労士試験の出題範囲すべてではなく、「基本的な事項」および「出題傾向の高い事項」に絞って暗記をする、と心得てください。
「すべてを暗記する」というのは、一見、覚悟のある潔い考え方と思えるかも知れません。しかしそれは、いわば玉砕覚悟の無謀な作戦。思考停止の状態なのです。
そうではなく、講義やテキスト記載内容などを分析し、暗記する部分を極力狭めることが重要です。
事例を理解する
法律の条文は表現が難解で抽象的なものが多く、何が言いたいのかイメージし難いケースも多々あります。
そのような場合は、具体的な事例に当てはめて考えるのがおすすめです。
たとえば、あなたやあなたの周りの方(家族など)について考えてみてください。
- どのようなルールに従って勤務先で働いているのか(労働法)
- 転職するとしたら、失業保険はもらえるのか(雇用保険)
- 病院で受診する際に、支払いはどうなっているのか(健康保険)
- 年金はどの程度貰っているのか(国民年金・厚生年金)
一見難しい制度でも、具体的な事例に照らし合わせて考えることにより、身に付きやすくなります。
本番の試験でも事例問題は出題されており、そうした問題への対策となるので一石二鳥といえるでしょう。
苦手科目を作らない
社労士試験では、苦手科目を作らないよう、まんべんなく暗記することが重要です。
社労士試験では、すべての科目に合格基準点がある
社労士試験では、すべての科目に合格基準点が設定されています。つまり、科目ごとに足切りがあるということです。どんなに他の科目で高得点を取ろうが、1科目でも足切りに引っかかってしまうと不合格となります。
これが、苦手科目を作ってはいけない理由です。
まずはどんどん先に進む
苦手科目を作らないためには、得意分野以上に不得意分野の勉強に時間を掛ける必要があります。
しかし、社労士の勉強を始めたばかりでは、
「どの科目が得意で、どの科目が不得意なのか」
が分からない人も多いでしょう。
そのため、学習当初は「まずはテキストを1周すること」「全体像を掴むこと」を目的として、どんどん先に進めていきましょう。
一通り学習しただけでは当然内容を覚えきれませんが、自分の得意・不得意な分野が見えて来るはずです。
自分の得意科目・苦手科目を把握したうえで、学習スケジュールを検討する
自分の得意・不得意が見えてきたら、正式な学習スケジュールを考えていきます。
「苦手科目を作らない」のが目標なので、不得意に思える分野に時間を割くようなスケジュールとします。
科目ごとのスケジュールが決まったら、それぞれの科目の基本事項と出題傾向が高い事項を明らかにして、暗記すべきポイントを整理しましょう。
横断学習をして暗記の効果を高める
しっかりと暗記するためには横断学習も有効です。
社労士試験では、複数の科目間で類似する事項が多いことが良くあります。
(例)
- 労災保険と健康保険の給付
- 国民年金と厚生年金の制度 など
これら複数科目の同一点・相違点を整理して暗記することで、それぞれの知識が頭の中に正しく定着することになります。
各科目で暗記すべき知識の混同が無くなることに加え、複数科目を一度に暗記できるわけですから、横断整理は非常に理にかなった学習方法だといえます。
社労士試験の暗記について まとめ
ここまで、社労士試験における暗記の適切な方法やポイントの押さえ方について解説してきました。
単なる丸暗記ではなく、理解すべきところはしっかり理解しながら、基本と出題傾向が高い点に絞って暗記することが重要です。
本記事でお伝えした様々な暗記の方法を実践して、ぜひ社労士試験の合格を勝ち取って欲しいと思います。