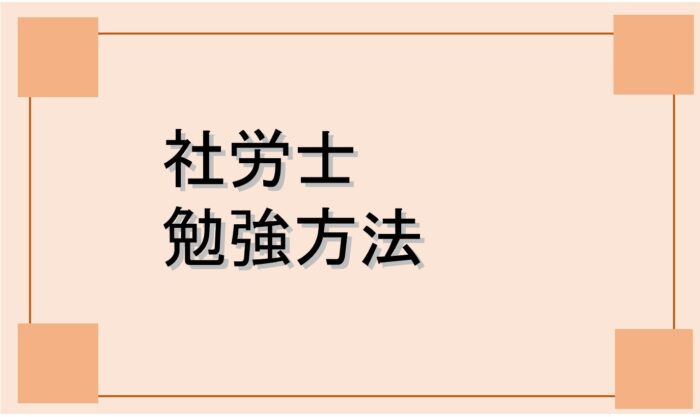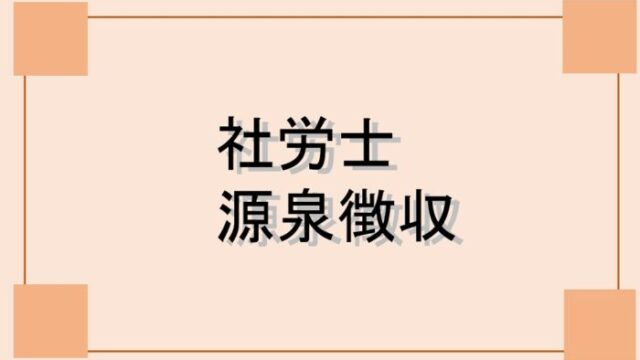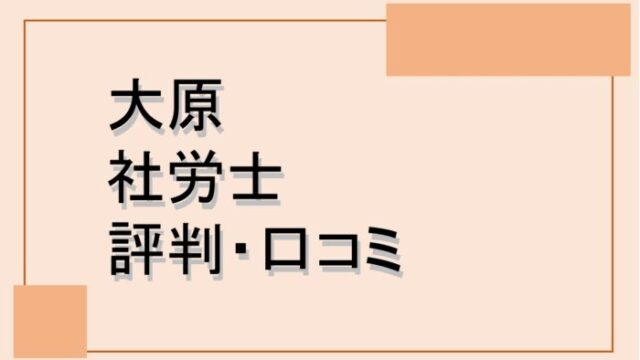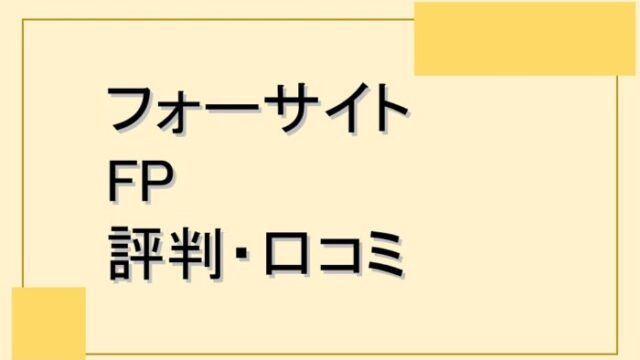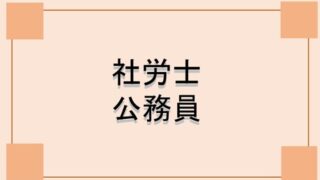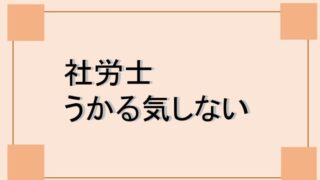社労士のおすすめの勉強方法【戦略編】
社会保険労務士(社労士)は他の士業と比較してみると、合格率の低い国家資格です。
難関の資格に合格するには、自分に合う勉強法で学習を進めていかないといけません。
自分に合う社会保険労務士(社労士)の勉強法を見極め、継続的に学習を続けるのが合格のために必須ですね。
人よりも明らかに勉強時間が短くても、社会保険労務士(社労士)に合格している人はいます。
逆に言えば、2,000時間も3,000時間も費やしても社会保険労務士(社労士)に合格できない人はいるでしょう。
この差は、日々の勉強法が大きく関わっていると言っても過言ではありません。
以下では社会保険労務士(社労士)のおすすめの勉強法を紹介していますので、何をすれば良いのかわからない方は参考にしてみてください。
なお、社労士試験の「最速合格勉強法」について、クレアールが、受験ノウハウの詰まった市販の書籍を、今だけ【0円】無料でプレゼント中です。
【0円】無料なので、ぜひ入手して読んでみてください。
<クレアールに応募すると、社労士受験生向けの市販の書籍「非常識合格法」がもらえる【0円】無料>
クレアールの社会保険労務士(社労士)講座に資料請求を行うと、全国の書店で販売中の社労士受験ノウハウ書籍が【0円】無料でもらえます。
試験に関する最新情報や、難関資格に「最速合格」するためのノウハウを凝縮。
社労士受験ノウハウ満載の市販の書籍が【0円】無料で進呈されるので、ぜひ入手してください。
まずはどの勉強法が自分に合っているのか考える
社会保険労務士(社労士)の試験対策に取り組む前に、まずはどの勉強法が自分に合っているのか考えるべきです。
他の資格試験にも該当しますが、社会保険労務士(社労士)の勉強法は
- 「独学」
- 「スクールへの通学」
- 「通信講座の利用」
の3つに大きくわけられます。
それぞれのやり方でメリットとデメリットに違いがありますので、簡単に見ていきましょう。
メリット:「テキストや問題集を買うだけで良いので金銭的な負担が少ない」「誰にも邪魔されずにマイペースで学習できる」「自分の好きな教材を組み合わせて勉強を進められる」
デメリット:「自分でスケジュールやカリキュラムを決める必要がある」「専門の講師の講義を受けたり質問したりできない」「法改正など最新の情報が入ってくるまで遅い」
メリット:「今までに培ってきたノウハウを提供してくれる」「講師による講義を直接受けられる」「やる気やモチベーションを高めて学習を継続できる」
デメリット:「仕事をしながらスクールに通学するのは大変」「受講料が高額で金銭的な負担が大きい」「自宅での予習や復習が疎かになりやすい」
メリット:「わかりやすい動画講義で試験対策ができる」「パソコンやスマホがあれば好きな場所で好きなタイミングで学習できる」「予備校への通学と比べると費用が安く済む」
デメリット:「独学と比べると初期投資がかかってしまう」「講師に質問をしてもリアルタイムで回答が返ってこない」「結局は一人での学習なので挫折することもある」
それぞれの方法で良い部分と悪い部分の両方があります。
例えば、誰かに強制されずに学習を進めたいのであれば独学、仕事が忙しくて勉強時間の確保が難しいなら社会保険労務士(社労士)の通信講座がおすすめです。
トータルでかかる費用にも大きな違いがありますので、どの方法で社会保険労務士(社労士)の試験勉強を行うのが良いのか考えてみてください。
スケジュール表やノートを作成する
社会保険労務士(社労士)の試験に合格するまでの勉強時間は、独学で1,000時間が目安です。
※社労士の勉強時間については、以下の記事も参考にしてください。
https://syaroushi-ganba.com/syaroushi-benkyo-jikan/
スクールへの通学や通信講座ではもう少し短い時間で済みますが、長い期間がかかる点では変わりありません。
仕事をしている社会人は限られた時間を社会保険労務士(社労士)の勉強に費やす必要がありますので、日々やることのスケジュール表やノートを作成すべきです。
最初にスケジュール表やノートを作成して勉強の流れを押さえておくと、試験日までにやるべきノルマが見えてきます。
もちろん、最初に決めたスケジュール通りに勉強が進まないことも多いため、土日や休日の勉強時間を増やして調整していきましょう。
ボリュームが少なくて予定以上に勉強が進んだ時は、積極的に前倒しで学習してスケジュールを組み替えればOKです。
テキストや参考書を読み込んで基礎を理解する
社会保険労務士(社労士)の試験範囲はとても広く、次の10科目を全てこなす必要があります。
- 労働基準法
- 労働安全衛生法
- 労働者災害補償保険法
- 雇用保険法
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
- 労務管理その他の労働に関する一般常識
- 社会保険に関する一般常識
- 健康保険法
- 国民年金法
- 厚生年金保険法
全科目合計で7割近くは得点しないといけませんし、科目ごとでも足切りがあります。
そのため、まずは社会保険労務士(社労士)のテキストや参考書をしっかりと読み込み、基礎知識を理解することから始めましょう。
通信講座を利用している方は、テキストに合わせて社会保険労務士(社労士)の動画講義を聞いて理解度を深めていきます(スマホだけで完結するものもあります)。
社会保険労務士(社労士)に限らず、資格の勉強でアウトプットを優先している方は少なくありません。
問題集の繰り返しは重要ですが、問題を解くのはテキストや参考書を一通り読んでから行うべきですよ。
断片をつなぎ合わせた知識は脆弱ですので、芯のある知識を構築するに当たって「読みやすい」「わかりやすい」というテキストが欠かせません。
社会保険労務士(社労士)の試験勉強でおすすめのテキストや参考書は、こちらのページで紹介していますので参考にしてみてください。
https://syaroushi-ganba.com/syaroushi-osusume-text/
科目の勉強の順番を意識する
社会保険労務士(社労士)の試験科目は、下記のように勉強の順番を意識してみるべきです。
- 関連性のある科目を続けて学習する
- 苦手科目を早めに攻略する
- 重要性の低い科目や暗記比重の重い科目は後ろに回す
例えば、国民年金法と厚生年金保険法は二階建て年金制度になっているため、共通している部分が多くなります。
労働者災害補償保険法と健康保険法は原因が異なるだけで中身は共通している部分が多いので、続けて学習した方が理解度を深められる科目です。
中でも「労務管理その他労働に関する一般常識」は難易度が高く、毎年何が出題されるのか予想がつきません。
かと言って基準点の足切り対策も重要ですので、予備校や通信講座の予想問題集を有効活用すべきです。
過去問で頻出論点や出題傾向を掴む
社会保険労務士(社労士)の試験を攻略するに当たり、過去問は欠かせないアイテムです。
基礎力なくして社会保険労務士(社労士)の試験は突破できませんので、「テキストや参考書で基礎固めする」⇒「問題集をひたすら解く」という繰り返しを意識しましょう。
社会保険労務士(社労士)の本番の試験では、次の問題が出題される傾向があります。
- 過去から出題された角度を変えた類似問題
- 以前と同じような焼きまわし問題
科目や単元によっては、毎年のように焼きまわしされている問題も少なくありません。
過去問を使えば社会保険労務士(社労士)の試験の頻出論点や出題傾向を掴むことができますので、合格基準点に達するために必要な存在ですね。
しかし、1科目だけでも何百ページ・何百問と量が多いため、全科目全問をこなすのは現実的ではありません。
仕事をしながら社会保険労務士(社労士)の合格を目指す方は勉強時間が限られていますので、頻出事項や重要論点を中心に過去問を解いていくのがベターです。
五肢択一形式の過去問ではなく科目ごとにわけられている一問一答形式の過去問を使うと、分野別や単元別の勉強を効率良く進められます。
社会保険労務士(社労士)の試験で過去問対策がおすすめの理由と、過去問の選び方についてはこちらのページをご覧になってください。
https://syaroushi-ganba.com/syaroushi-kakomon/
反復学習を心掛ける
参考書を読み込むにしても問題集をひたすら解くにしても、反復学習を心掛けるのは社会保険労務士(社労士)の効果的な勉強法です。
わからない部分をそのまま放置するのではなく、重要な科目を中心に理解度を深めることで合格に近付きます。
具体的に社会保険労務士(社労士)の試験勉強でどうやって反復学習をすれば良いのか見ていきましょう。
- 解けなかった過去問は解説を読むとともに参考書に戻って復習する
- 学習範囲や押さえるべきポイントを把握して記憶への定着を図る
- 全科目の学習が一通り終わったら周回学習をして満遍なく反復する
最初に勉強した科目は一通り終わった段階で前の知識になっていますので、忘れている部分も少なからず出てきます。
リピート学習によって少しずつ記憶に定着していくため、「まずはXヵ月間で全科目を回す」「次は前回の半分の時間で全科目を回す」とスパンを短くするのがコツです。
アプリを使ってスキマ時間を徹底活用する
社労士試験は難関国家資格のため、テキストや問題集のボリュームはかなり大きいです。また、合格まで長時間掛かるため、通勤・通学のスキマ時間を上手く活用できれば非常に有利になるでしょう。
そんなニーズを満たすのが「社労士試験用のスマホアプリ」です。
スマホアプリを使えば、重いテキストや問題集を持ち歩くことなく、混雑した電車内でも無理なく学習を進めることができます。
無料で使えるアプリもありますので、まだ社労士試験用のアプリをチェックしたことのない方は、ぜひチェックしてみてください。
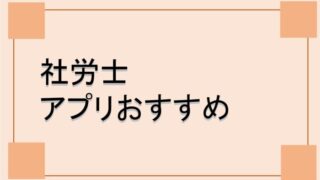
模擬試験を受験する
社会保険労務士(社労士)の本番の試験は、毎年8月の最終日曜日です。
4月から6月にかけての時期は、基礎固めから問題演習に勉強内容を切り替えていきます。
7月を過ぎた辺りからは、社会保険労務士(社労士)の模擬試験を積極的に受けましょう。
資格の大原やTACなどの大手のスクールでは、社会保険労務士(社労士)の模試が実施されています。
社会保険労務士(社労士)の勉強法の中でも模擬試験は次の3つの理由で必須ですよ。
- 他の受験生が受けている中で過度に緊張せずに試験に臨む練習ができる
- 「この科目は○○分をかけて解く」という時間配分の訓練に繋がる
- 合格を左右する選択式試験の問題が本試験でも出題されることがある
- 自分では考えもしなかった不得意な部分や科目が見つかりやすい
何回とは決まっていませんが、社会保険労務士(社労士)の模擬試験は2回の受験をおすすめします。
1回目の模擬試験で時間配分や解く順番の練習を行い、ダメな部分を軌道修正して2回目の模擬試験は本番モードで臨みましょう。
※社労士の模試受験のポイントについて詳しくは、下記の記事も参考にしてみてください。
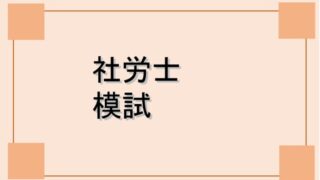
■
また、最近は学生のうちから社労士資格を目指す方が増えているようです。大学生が在学中に社労士を取得するメリットやデメリットについては、下記記事で詳しく解説していますので、よろしければこちらもどうぞ。
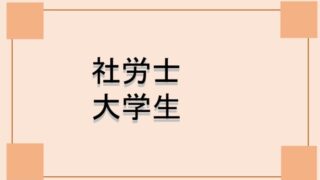
社労士のおすすめの勉強方法【リサーチ編】
ここまで、社労士試験のおすすめ勉強法の戦略について説明しました。「すぐにでも勉強を始めたい!」とモチベーションアップした方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、ちょっと待ってください。孫子の言葉に「敵を知り己を知れば百戦危なからず」というものがあります。つまり「敵=社労士試験そのもの」をまずは知っておく必要があります。
以上の理由により、以下では社労士試験の概要をまとめました。
試験日程・スケジュール
社労士試験の申し込みの期間や試験日、合格発表日は以下のとおりです。
| 社労士試験の申し込み期間 | 毎年4月中旬から5月末日まで |
| 社労士試験の試験日 | 毎年8月の第4日曜日または第5日曜日 |
| 合格発表日 | 毎年10月末~11月初旬頃 |
受験者数と合格率
受験者は毎年4万人前後であり、過去10年の合格率推移は以下のとおり平均6%前後となっています。
平成24年度:7.0%
平成25年度:5.4%
平成26年度:9.3%
平成27年度:2.6%
平成28年度:4.4%
平成29年度:6.8%
平成30年度:6.3%
令和元年度 :6.6%
令和2年度 :6.4%
令和3年度 :7.9%
合格基準
社労士試験の合格基準は、おおむね以下のとおりです。
- 選択式試験:総得点で7割程度以上(原則として、各科目3点以上)
- 択一式試験:総得点で7割程度以上(原則として、各科目4点以上)
選択式試験と択一式試験の両方で総得点をクリアするだけではなく、全ての科目を基準点以上にしないといけません。
社労士試験の難易度
社労士試験の難易度(偏差値のランキングによる難易度)
ここでは、某掲示板サイト等からまとめた「資格難易度・偏差値ランキング」をご紹介します。※実際には国家資格試験に偏差値は存在しないので、あくまで目安と考えてください。
上記のランキングによると、税理士・会計士・司法書士の難易度は偏差値65~64と、司法試験に次いでいます。
社労士・中小企業診断士・行政書士は「働きながら取得できるレベルとしては一番難しい」と良く言われますが、偏差値としては60~59。
総合的に見ると、社労士の難易度は、難関国家資格(士業)の中では、標準的といえます。
本当に独学で社労士に合格できる?
独学では勉強が進まない
ここまで社労士試験の概要を見てきましたが、平均6%前後の低い合格率・各科目ごとに設定された基準点など、かなり難しい試験ということが分かったかと思います。
この記事の冒頭で、勉強方法には「独学」「通学」「通信」の3つがあることを説明しました。この中で独学を選ばれる受験生も多いのですが、正直、まったくの独学はおすすめできません。その理由は以下のとおり。
- 自分で学習スケジュールを立てなければならない
- テキストや問題集も自分で選ぶところから始めなければならない
- ベテラン講師の分かりやすい講義を聴くことができず、テキストを読んで理解しないといけない
正直、これらはかなりのハンデです。「そうは言っても、独学以外は費用がかかるから・・・」と敬遠している方もいるかも知れません。
しかし、スマホ対応通信講座であれば4万円台から受講できるコースもあります。4万円の投資で、1年以上もかかる社労士試験勉強をグッと効率化できますので、まだスマホ対応通信講座をチェックしたことのない方は、ぜひチェックしてみてください。
おすすめの通信講座は、フォーサイトとスタディング
おすすめのスマホ対応通信講座は、フォーサイトとスタディングです。
4万円台からと、抜群のコストパフォーマンスを実現しつつ、合格のために必要な機能を徹底的に充実させた「スタディング」
スタディングより割高ではあるが、合格実績が高く、フルカラーテキスト(冊子版)の標準添付や質問対応にも力を入れた、フルスペック志向の「フォーサイト」
どちらを選んでも間違いはありませんので、あなたが納得できる講座を選んで欲しいと思います。
スタディングが気になる方は、公式サイトにて、動画講義やテキストをチェックしてみてください。
=>「スタディング 社労士 通信講座」の無料お試しはこちら
「スタディング 社労士通信講座」の口コミ・評判のチェックは、以下の記事をどうぞ。
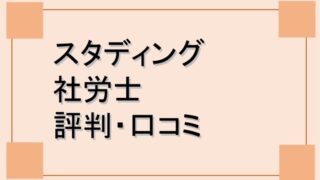
また、フォーサイトの方が気になる方は、ぜひ公式サイトに行って、動画やテキストのサンプルをチェックしてみてくださいね。
=>「フォーサイト 社労士 通信講座」の無料お試しはこちら.
「フォーサイト 社労士通信講座」の口コミ・評判のチェックは、以下の記事をどうぞ。
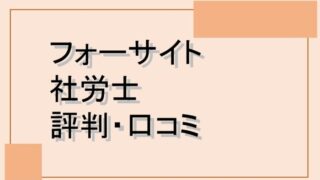
まとめ
社会保険労務士(社労士)のおすすめの勉強法についておわかり頂けましたか?
参考書を読み込んだり問題集を解いたりと基本的な事柄について説明しましたが、社会保険労務士(社労士)の試験に合格するためには欠かせないポイントです。
しかし、試験勉強を進める中でやる気やモチベーションが下がることがありますので、次の対策を行ってみましょう。
- なぜ社会保険労務士(社労士)の合格を目指すのか目的を再確認する
- 時には自分を褒めてあげる
- 資格を取得した後に活躍する自分を想像する
社会保険労務士(社労士)の試験勉強は長丁場になりやすいので、長く学習を継続する努力をしてみてください。