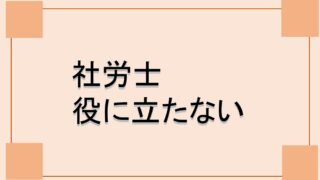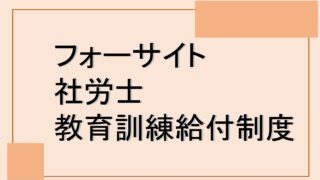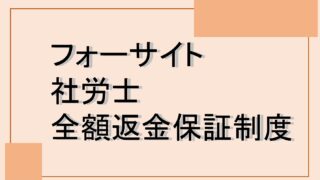社会保険労務士(社労士)の連合会とは?
全国社会保険労務士会連合会(社労士会の連合会)とは、社会保険労務士法第25条の34に基づいて設立された特別民間法人です。
厚生労働大臣の認可を受けて設立された全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士(社労士)の資格を持つ方の資質の向上と業務の改善進捗を図るために様々なサポートをしています。
以下、全国社会保険労務士会連合会の業務内容を詳しくまとめてみました。
事務指定講習や免除指定講習
全国社会保険労務士会連合会では、国家試験の受験者や合格者を対象に次の講習を実施しています。
- 国家試験受験者対象の社会保険労務士試験試験科目免除指定講習(修了すると試験の一部の科目が免除される)
- 国家試験合格者対象の労働社会保険諸法令関係事務指定講習(修了すると社労士の登録を受けられる)
社会保険労務士(社労士)の資質の向上を図るために、業務に関する研修を行っているわけですね。
※事務指定講習については、下記の記事も参考にしてください。
https://syaroushi-ganba.com/syarou-jimu-shitei-kousyu/
無料相談会やセミナー
全国社会保険労務士会連合会は毎年10月に社労士制度推進月間と定め、社会保険労務士(社労士)の無料相談会やセミナーを行っています。
社会保険労務士(社労士)のセミナーは次の2つです。
- 資格保有者が相談員となって雇用や労働に関する相談に無料で対応する「雇用・労働・年金に関する無料相談会」
- 中小企業の事業主や総務担当の課題となる事案について社労士がわかりやすく解説する「社労士会セミナー」
セミナーのテーマは都道府県の社労士会で違いがありますので、詳細は公式サイトで確認しておきましょう。
倫理研修
全国47都道府県にある社労士会では、社会保険労務士(社労士)の職業倫理を保持する目的で倫理研修を実施しています。
社労士会所属の社労士は、5年に1度、倫理研修を義務付けられています。
ここでは、社会保険労務士(社労士)のための倫理研修についてまとめてみました。
- 受講対象者:平成30年度は平成29年度(平成29年4月1日~平成30年3月31日)に登録した会員
- 実施時期:実施日及び会場は47都道府県にある社労士会が決める
- 実施方法:集合形式による倫理研修実施の意義や労士の職業倫理及び事例の解説
- 受講料:無料(交通費等にかかる実費は自己負担)
- 講師:全国47都道府県にある社労士会で決まる
経営労務診断サービス
全国社会保険労務士会連合会では、経営労務診断サービスが行われています。
経営労務診断サービスを受けることで、企業の健全性のアピールや企業価値の向上が可能です。
企業側からみた、経営労務診断サービスのメリットは以下のとおり。
- 労務管理の健全性のアピールで企業の信頼性の担保を図ることができる
- 社労士による確認や診断を毎年受けることで法令を遵守しているか定期的にチェックできる
- 適正な労務管理に取り組む企業だとPRして優秀な人材を確保できる
多様な働き方の推進による企業の持続的な成長をサポートするためのサービスだといえるでしょう。
労務診断ドック
全国社会保険労務士会連合会は、「働き方改革支援宣言」の取り組みとして労務診断ドックを実施しています。
労務診断ドックが具体的にどのようなサービスなのか見ていきましょう。
- 社会保険労務士(社労士)が働き方改革取り組み宣言シートを使い、企業の労働環境の実情を無料で診断してくれる
- 働き方改革取り組み宣言シートへの回答で、今後の改革のポイントについて気付くことができる
- 企業の気付きが労働環境改善への決意や動機付けになり、人材を大切にする会社の実現の第一歩になる
- 働き方改革に取り組む企業として求職者たちにアピールできる
顧問社労士がいない企業は、最寄りの都道府県の社労士会に問い合わせる形で労務診断ドックを受けられます。
社会保険労務士(社労士)になるには連合会への資格登録が必要なの?
国家試験に合格すれば、「晴れて社会保険労務士(社労士)になれる」「社会保険労務士(社労士)として仕事ができる」とイメージしている方はいませんか?
難関の資格試験に合格して、ホっと一息つく方は多いのではないでしょうか。
しかし、社会保険労務士(社労士)の試験に合格して得られるのは資格のみで、実際に業務を遂行するには全国社会保険労務士会連合会への登録が必須ですよ。
社会保険労務士(社労士)を名乗って業務を行う場合は、必ず登録しないといけないと法律で定められています。
全国社会保険労務士会連合会への登録をせずに社会保険労務士(社労士)として働いて報酬を得ると、100万円以下の罰金が課せられますので注意しましょう。
ここでは、社会保険労務士(社労士)として登録するメリットとデメリットを解説していきます。
- 社労士登録のメリット:きちんと登録した人だけが業務を請け負えるため、参入障壁となり仕事の安定化につながる
- 社労士登録のデメリット:登録には高額な費用がかかる。また、試験をパスしてすぐに登録できるわけではないので、業務開始までタイムラグが発生する
試験に合格してからすぐに社会保険労務士(社労士)として働く予定でないのであれば、全国社会保険労務士会連合会への登録を見送るのも選択肢の一つです。
社会保険労務士(社労士)が連合会に登録する流れ
社会保険労務士(社労士)として働くために、どのような流れで連合会に登録するのかまとめてみました。
- 毎年1回に渡って実施される社会保険労務士(社労士)の試験に合格する
- 2年間以上の実務経験を積むか連合会の事務指定講習を修了する
- 全国社会保険労務士会連合会に備える社労士名簿に登録を受ける
社労士の資格を有する者が全国社会保険労務士会連合会の名簿に登録すると、晴れて社会保険労務士(社労士)になることができます。
全国社会保険労務士会連合会の登録を受けた時に、都道府県の社労士会の会員にもなります。
入会するのは、開業する社労士事務所や勤務先事業所の都道府県の社会保険労務士会になります。
試験に合格してから社会保険労務士(社労士)として働き始める予定の方は、必要書類を準備・作成して登録手数料や会費とともに提出しましょう。
社会保険労務士(社労士)の登録申請に必要な書類
社会保険労務士(社労士)の登録申請には、次の書類が必要です。
- 社会保険労務士登録申請書(様式第1号)
- 社会保険労務士試験合格証書(写し)
- 従事期間証明書(様式第8号)、または、事務指定講習修了証(写し)
- 住民票の写し(提出日前3ヵ月以内に市区町村から交付されたもの)
- 写真票(縦3cm横2.5cmで正面向の鮮明な写真)
- 戸籍抄本、個人事項証明書又は改製原戸籍
- 通称併記願(通称名の使用を希望する者)
社労士の登録申請の流れや必要書類に関しては、全国社会保険労務士会連合会の公式サイトでも記載されています。
参考:https://www.shakaihokenroumushi.jp/qualification/tabid/223/Default.aspx
社会保険労務士(社労士)の登録に必要な費用
社会保険労務士(社労士)に登録しようか悩んでいる方が多いのは、入会費や年会費などの費用がかかるからです。
以下では、社会保険労務士(社労士)の登録に必要な費用をまとめてみました。
- 事務指定講習費用(2年間以上の実務経験がない者):77,000円(税込)
- 全国社会保険労務士会連合会への登録手数料:30,000円
- 登録免許税:30,000円
- 各地域の社労会への入会金(東京都で開業):50,000円
- 各地域の社労会の年会費(東京都の場合):96,000円
各地域によって、入会費および年会費は異なります。詳細は所属予定の都道府県の社労士会で確認しましょう。
どの地域に住んでいても、社会保険労務士(社労士)として仕事を始めるには高額な登録費用がかかります。
また、独立開業と勤務で登録の費用が変わるため、どちらの道に進むのか決められずに社会保険労務士(社労士)の登録を見合わせる方も少なくありません。
全国社会保険労務士会連合会への登録は、社会保険労務士(社労士)としての将来をしっかりと見通してからにしてください。
※社労士登録の初期費用や維持費については、以下の記事も参考にしてください。
https://syaroushi-ganba.com/syaroushi-hiyou-ijihi/
まとめ
社会保険労務士(社労士)の連合会がどのような業務やサポートをしているのかおわかり頂けましたか?
社会保険労務士(社労士)の資格を持つ方への講習や研修に加えて、全国社会保険労務士会連合会では経営労務診断サービスや労務診断ドックも行っています。
また、社会保険労務士(社労士)として働き始めるには、全国社会保険労務士会連合会への資格登録が必須です。
費用は高額ですが、社労士として活動するには登録を避けては通れませんので、これから社労士を目指す方は、覚えておいてください。
| この記事の監修者 | |
| 氏名 | 西俊明 |
| 保有資格 | 中小企業診断士 , 宅地建物取引士 , 2級FP技能士 |
| 所属 | 合同会社ライトサポートアンドコミュニケーション |